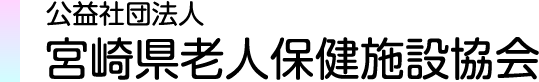似たような話としては、介護者と要介護者の話におきかえると・・・以前は入浴後は自分で更衣を行っていましたが、時間がかかるので、介護者が更衣を介助するようになりました。
すると、この利用者様は自分で更衣をすることはなくなり、待つようになりました。更衣をやっていただけるものとして、待つ習慣がついてくるようになりました。
いわゆる、日々の業務のなかの「習慣が生み出すリスク」の1つではないでしょうか?
この状況を作っているのは本人様だけでなく、ケアを提供している私達にあるのかなという視点をもつことが大事だと思います。
対策としては・・・できるだけ本人様にしていただけるように心掛け、本人様の手などを触って(添えて)行っていただくこと。つまり、習慣化を意識していくこと(条件反射?)になりリスク減少につながるのではと考えます。日々麻痺していく感覚の中でこういうことに気づくだけでも違うのではないでしょうか?
(2)環境の相違が生み出す転倒リスク?事例(2)として、「生活の中で利用者様は自分に合った車椅子で両足駆動をしていました。ある日、その車椅子が故障しました。」だから、施設にあるやや大きめの車椅子をしばらく使うことになりました。
利用者様はいつも通り車椅子を両足で駆動しようとして、車椅子からの滑り落ちの事故がありました。では、なぜ滑り落ちたのでしょうか?
事故理由として、本人にとって不慣れな車椅子だったからとか、高齢であったから、認知症であったからというように、本人様のみの原因でしょうか?
利用者様は両足駆動のため、施設の車椅子では床面に足が届かなくなり、いつもより浅く座った状態で駆動していた為滑り落ちがあったのではないだろうかと考えられます。
事例として、「車椅子のブレーキ忘れによる転倒事故」ですが、同じ状況です。
事故理由として、利用者様が使用していた施設の車椅子は、ブレーキが固く利用者様自身ではブレーキが掛けられないために起こったという事も考えられます。
例えば車椅子に空気を入れて、そのまま確認しないで、ただ入れましたという事ではブレーキが固くなっていることも多くあります。高齢者や麻痺のある方はどうでしょう?空気を入れたら確認をして調整するひと手間で防げる事もあります。利用者様の立場で考えてみて気づきましょう!という事です。
例えば左ハンドルの車と右ハンドルの車では、ウインカーとワイパーが反対になっていることは、頭では理解していますが、ついつい間違ってしまう経験はないでしょうか?
身体が覚えてしまっている為に、このように車椅子が変わってもいろんな事故が起こってしまう、「環境の相違が生み出すリスク」の1つではないかと思います。
対策としては、できるだけ同環境・同条件に近いものを使用する。できるだけ使い慣れたものを提供する。本人様の立場をできるだけ理解する事が大事ではないでしょうか?
逆に考えれば、新しい環境(不慣れな環境)では注意が必要ということになります。(事故が起こり易い)。
(つづく)