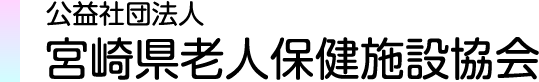研究課題、そして研究方法が決まれば、次に行うのが「研究目的の明文化」。まず「研究の顔」となるタイトルを付けるにあたっては、「研究が何を求めているかを大づかみに理解できるもので、副題をつけることで研究の限界や、現状を述べることもある」とのこと。「日中の傾眠や夜間不眠がある。この利用者の生活リズムが調整できないか」という事例について、小野先生は「認知症高齢者に対する安眠へのケアに関する一考察 ?昼夜逆転に対する生活リズム調整への取り組みを振り返って?」というタイトルを示し、「『一考察』とつけることで、読む人に“何かが見いだせている“と思ってもらえることができます」と説明。このほか、「認知症高齢者の傾眠や夜間不眠の要因 ~A事例の生活実態からの分析~」、「認知症高齢者の傾眠や夜間不眠を解消するケア方法 ~A施設職員のケア方法の分析から~」など、研究方法に即したタイトルのつけかたも教わりました。

そしていよいよ研究計画を立案し、研究の実施に入ります。研究計画は研究テーマに関する実施手順を示した設計図のようなもので、
(1)研究テーマ、(2)研究メンバー、(3)研究動機(テーマを設定した背景、自己の問題意識、研究の意義)、(4)研究目的(どのような成果を求めているか)、(5)研究方法(どのような取り組みが可能か:研究デザイン、研究対象、データ収集方法、分析方法)、(6)倫理的配慮(研究協力者へ同意を得る方法、人権の擁護、個人の不利益への対処)、(7)社会化の方法(どこの学会で発表するか、など)、(8)スケジュール、(9)その他(疑問、研究課題)・・・など、これまで吟味したことを記録に整理し、メンバーで共有していくために重要とのことでした。
研究計画に沿って実際に研究を行い、データ収集、データ分析をして抄録や論文を作成していきますが、「研究で得たものは、他の人には文字を通してしかわかりません。研究の成果を文章化し、報告することによって社会化ができます。力を入れて書いて行きましょう」と小野先生。そのポイントは「内容を浮き彫りにするための形式となっているか」、そして「他人に伝わる文章表現がなされているか」の2点とのこと。これを踏まえて抄録・論文の作り方を学んでいきました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
《抄録作成のポイント》
1.【はじめに】を書く
〇問題を自覚し、研究に取り組もうと思った動機について書く
〇テーマにつながる事実を端的に述べる
〇課題に対する社会的動向、先行研究で明らかにされていることおよび未解決な問題についてなどにもふれる
〇研究テーマとの整合性を考えて、この研究で何を明らかにしたいか、研究目的を書く
2.【研究方法】を書く
※【はじめに】や、研究目的との整合性を考えて、追試ができるようにわかりやすく記述する→?研究対象とデータ収集の方法(研究論理上の問題への手続きをふむこと)、?分析方法・手順、?倫理的配慮
3.【結果】を書く
〇得られた結果をすべてそのまま示すのではなく、研究テーマや研究目的を説明するのに必要な項目を選定して書く
〇表や図を効果的に用いる
〇事実を淡々と述べる
4.【考察】を書く
〇考察のねらいはディスカッションすること
〇結果で明らかになった事を自分自身で意味づけ、解釈した私見を他の研究者の意見(文献)と討論しあう過程を書く:?研究目的に照らしながら得られた結果を解釈し、意味づけていく。何がどこまで明らかになったか吟味する、?得られた結果を文献と照合しながら、従来の知見との共通性、または新たな知見が何かについて論じる。自己のなし得たことの評価をする
5.【まとめ】を書く
〇研究のすべての総括
〇研究目的と目標の簡単な説明、方法、結果、結論、意義に関する簡潔な記述
6.引用文献を書く
〇引用文献は引用順に書く。参考文献は、著者名の五十音順になど、法則性を持たせて欠く
〇引用文献の書き方:雑誌は「引用順番)著者名【共著者全員】:論文題名,雑誌名,巻(号):引用箇所の頁,発行年」の形で示す
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・