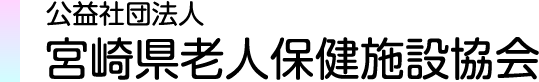ずっと昔の事ですが、「この『早春賦』の歌いだしの『はるはなのみのかぜのさむさや』とは、どういう意味なのか?」とちょっとした言い争いになったことがあります。ある人が「”春、花の実の、風の寒さや“じゃないのか?」と言い出したのです。「一体、何の花の実じゃろか??」と。すると、別な人が反論したのです。「違うが!”春はナァ、ノミのォ、風の寒さやァ“じゃないかと思うとよ」と。たしかに、ノミにとって寒風はさぞかしこたえることでしょうけど・・・(-_-;)。もちろん正しくは、「春は、名のみの、風の、寒さや」。文語調の歌詞は、漢字もままならぬ子供たちにとって、しばしば誤解と論争のタネとなっていました。しかしながら、この歌詞は推敲(すいこう)を重ね、一つ一つの言葉を織り上げて、春にはまだ早い里の風景を実に美しく描いている、と今になってしみじみと胸を打たれる思いです。
「立春が過ぎて、暦の上は春ということになっているのだが、それは全く名ばかりのことで、吹き付ける冷たい北風が身に染みることだよ。谷間に住むウグイス達も、あの”ホーホケキョ”という美声を山里に響き渡らせたくてうずうずしているのだろうが、『こんなに寒かったらまだ出番じゃないようだね』と声も立てずにじっとしているよ」というのが1番の歌詞の意味でしょうか。だけど、こんなにぐちぐちと言うよりも、「春は名のみの風の寒さや 谷の鶯歌は思えど 時にあらずと声も立てず 時にあらずと 声も立てず」と言葉を整え、8分の6拍子のメロディーに乗せた方が、心にスーッとしみてきます。吉丸一昌という詩人、そして、中田章という作曲家、素晴らしい日本の歌をこの世に残してくれた、とありがたい気持ちで一杯です。
この『早春賦』、2番になると「こおりとけさりあしはつのぐむ」(冬の間張っていた氷がすっかり融解し、”葦”という植物が角のように芽を出して来たことだよ)、さらに「さては時ぞと思うあやにく」(さあ、いよいよ芽吹きの時を迎えた、と思ったものの残念なことに)と続きます。「”足“がどうしたというのか?」だとか、「”あや肉“とはどんな肉か」と、やはり疑問に思いはしたのですが、子供の頃にはとにかく耳で覚えたままに、「あしはつのぐむー」とか、「おもうあやにくー」とやっていました。
一方、今のヒットソングの歌詞は、ほとんど全てが口語体。言文一致運動を進めた二葉亭四迷が、もし時代を超えて今にやって来て、現代の「名曲」を聴いたらどう思うだろうか、「あの頃の未来に、僕らは立っているのかなー♪」と口ずさむだろうか、と興味あるところです。それはともかく、『早春賦』に見られるような文語体による歌は、わかりにくい部分があるかもしれないけれども、それが理解できるようになると、却ってその素晴らしさがわかるのではないか?と考えます。
立春が過ぎ、暦の上では春なのですが、相変わらず寒い日が続いています。「春と聞かねば 知らでありしを 聞けば急かるる胸の思いを いかにせよとのこの頃か いかにせよとのこの頃か」(もし「暦の上は春になっている」という情報を耳にしなかったら、心がときめくこともなかったろうに、それを聞いてしまったものだから、本当の春の訪れが心待ちでならなくなってしまったよ。ああ、この抑えられない胸躍る気持ちを一体どうしたらいいというのだろうか)と、『早春賦』を歌いながら、この名曲の素晴らしさを堪能するとともに、暖かい春の日差しが注ぎ始める始める日の訪れを待ちたいと思います。