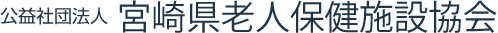パンさえあれば
パンさえあれば、たいていの悲しみは耐えられる」と言ったのはスペインの作家、セルバンテス(夏村波夫編、『生きる勇気がわく言葉』)。『ドン・キホーテ』の著者として有名ですが、ずーっと”ドンキ・ホーテ”と勘違いしてました<(_ _)>。
この名言も同書の中の言葉ですが、それを思い出すような11月15日付け朝日新聞の投稿欄「声」にありました。そのタイトルは「母のために持ち帰ったパン」。神戸市の70代の主婦の方(Aさんとします)の投稿でした。
戦時中、小学生だったAさんは楽しみだった給食のパンを半分残して持ち帰ろうと画策。食糧難で食べ残しなどもってのほか。教師からも厳しく禁じられていた中、強烈な罪悪感に打ち勝ってまで強行に及んだそのわけを、母親に問いただされてAさんは答えたのです。「お母さん食べて」・・・。そうです。Aさんは自分よりおなかをすかしている母親に食べさせたい一心で、担任教師の目を盗み、半分残したパンを給食袋に隠し入れて持ち帰ったのです。わずか20行の文中、ここまででまだ14行。もう涙があふれて先が読めません。ティッシュで目やら鼻を拭き拭き。一段落して先を読みました。
理由を聞いた母親はAさんをぎゅっと抱きしめてたった一言。「先生のお言いつけを守りましょうね」・・・。もうだめ(ToT)。ティッシュが、ティッシュがありません。なんと感動的な20行!!一途に母を思う子の心のなんとけなげなるかな!。そして規則を破ったAさんを言葉でとがめ、身体で感謝する母から子への愛情の深く広きことよ!飽食の時代にある今日では想像しがたい行為ですが、そういう時代だからこそあり得た母と子の絆の固い結びつきを思い知らされた投稿でした。
短文ではありませんが、第二次世界大戦中、ハンカチに包まれたパンのおかげで艱難辛苦に打ち勝ち、死線を乗り越え妻の待つ我が家に帰り着いたという話では、ムンテヤーヌの『一切れのパン』があまりにも有名です。自宅で妻に事の成り行きを説明する主人公がパンを出そうとハンカチを広げるとそこにあったのは・・・。国語の教科書にも掲載されたこともある感動話です。
感動話で言えば、二十年以上前に大はやりした、いい話がありました。毎年大晦日の夜になると母子三人がそば屋を訪れ、かけそばを一つだけ注文し、三人で食べ合うという感動話、そう、「一杯のかけそば」です。国会で取り上げられたり、「実話か?創作か?」などと物議をかもしたり、映画化までされましたっけ。
それはともかく、「給食への幼い思い、戦争とつながる思いは今は遠いは今は遠い風景となった」で締めくくられたAさんの体験談。何度読み返しても心が温まります。コピーしてみんなで回し読みしているところです。