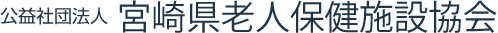「高齢者施設での看取り」学びました(看・介部会:その11)
次に市原理事長は「誰に看取ってもらいたいか」という話を始めました。「看取りの主人公は家族だと思います。もちろん家族がいない人もいます。だったら例えば皆さんだったりするかもしれません。そういう意味では家族にかわる”疑似家族”です」と述べた上で、「私は”病院での死”と”在宅での死”とでは質が違うとこの頃思っています」と切り出し、次のように説明しました。
「病院ではモニターがついています。モニターに血圧や心電図がデジタルで表示されていますよね。家族はそれをじーっと見ています。『看取った経験があります』と言っても、”デジタルで死ぬまでのプロセスがわかった”ということです。それに対し在宅だとモニターはありません。そうするとどうやって看取っているかというと、手を握ったり声を掛けたり、身体をさすったりしてアナログで看ています。アナログの看取りというのは”五感”です。自分の五感を働かせて、その人のそばにいるということです。そういう意味では私達は家族が悔いなく看取れるように支えていくことが必要なのではないかと思います。遠くにいる家族にも『今こういう状況ですよ』とメールで日々お知らせすればいいわけです。そうするとご家族が来られなくても状況が共有できます。そうしていくと家族が『どうしてこういうことになったんですか?何かあったんじゃないですか?』と言うことはありません」。
このように在宅で看取りを行うことは、大切な人の死を通して、初めて人間関係が豊かになるとともに、「死」から「生きる」ことを学ぶことにもつながると説いた市原理事長は、家族が悔いのない看取りが出来るように支え、その時間と空間を提供する事が大切であるとして、「看取りの支援と補完」の重要性を参加者に力説しました。
また「尊厳死は、日々の生活の延長線上にある」というスライドを示した市原理事長。「毎日毎日の延長線上の最後が『その人が亡くなった日』ということになります。従って『はい、ここからが看取りです』というのがはっきり始まるわけではありません。そこまでのプロセスだと思います」と述べたのに続き、日本医師会と産経新聞社が共催で地域の医療現場で長年にわたり、健康を中心に地域住民の生活を支えている医師にスポットを当てて顕彰する「第2回赤ひげ大賞」を平成26年に受賞した滋賀県の小鳥輝男医師の「幸せな最後」という言葉を紹介しました。
「幸せな最後とは」
〇自宅で家族に見守られ静かに逝く、に尽きるでしょう。
〇孫やひ孫が走り回り、家族は逝く人をダシに酒を飲みつつ、思い出話に花を咲かせる。
〇おい、もうそろそろだの声で皆が枕元へ。
〇かかりつけ医が往診してきて脈をとり「ご臨終です」
〇皆が悲しみの心の中に「ホッ」との安堵感が
〇涙はあるが笑顔になる。
〇昔はみんなこうだった