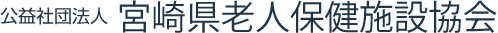「高齢者施設での看取り」学びました(看・介部会:その5)
開口一番、「『人生の幕を閉じるとき、どこで、どのように、誰に看取ってもらいたいか?』皆さんも自分のこととして考えてみて下さい」と市原理事長は参加者に問いかけました。そして「『住み慣れた自宅で過ごしたい』、『最後まで口から食べたい』、『延命治療はせず、自然に生を全うしたい』、『家族に看取ってもらいたい』と皆さんだいたいおっしゃいます。だけど今の社会はそれがなかなかそうはいかない現状です」として次の点を指摘しました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【最後まで家で暮らしたい・・・、家で看取ってやりたいけど・・・】
〇急性期病院は→治療の対象でなければ入院できない。高齢の場合、がんの治療はできても、環境の変化でADLが低下してしまい、家に帰れない。
〇緩和ケア病棟は→がんとエイズに限られ、高齢でがんになり、認知症があると入院の優先順位が下がる。
〇介護施設は→年齢や障害の程度に限度(介護度)。医療的な依存度が高いと入居条件に合わないと敬遠される。
〇自宅は→老老介護や一人暮らしが増えていて、介護力が弱くなっている。
〇家族は→看取ってやりたいが、遠方に暮らしている。別世帯で、昼間は仕事で介護できない。看取りの経験がなく、何かあった時不安。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本の人口構造の変化をスライドに示しながら、1人の高齢者を2.6人で支えている現在社会構造は、少子高齢化が一層進行すると2060年には1人の高齢者を1.2人で支えるようになると想定されていると説明。その上で今はほぼ9割の人が病院などで亡くなっている現状に触れるとともに、超高齢社会で今後亡くなる人が増えることなどをスライドに示しながら、「『私たちはどこで亡くなるのか?』という時代に入っています」と述べ、介護施設などの充実が必要だとしました。
このようなことから、「『病院でなければ死んじゃいけないのか?病院でなければ死ねないのか?』と思っている人も増えています」と説明した市原理事長は、そのもう一つの背景として、「老化に伴って自然に亡くなる方のモデルが身近になくなった」ことをあげました。「『病院じゃないと心配だ』という人がいます。『栄養がない状態になったら心配だ』とおっしゃ方がいます。だけど亡くなるとき、栄養は無くなります。死ぬときは栄養を吸収できない身体になっていきます。そういうモデルが身近にないために、病院で亡くなることが一般化してしまっています。『家で看取ってやりたい』と思っていても、いざ急変すると救急車を呼びます。それは『ともかく命を助けて下さい』とお願いすることです。そうすると本人が『最後まで家で暮らしたい、延命治療はしたくない』と思っていても、病院で最後を迎える可能性が高くなります」と、”どういうプロセスをたどって死に至るか?”がわからないことから来る不安が、「最後まで家で暮らしたい」、「家で看取ってやりたい」という希望があるにもかかわらず、病院で最後を迎えることにつながっていると指摘した市原理事長は、さらに「これは家族だけでなく、施設の若い職員にも言えます」と述べ、人が亡くなるプロセスを前もって理解しておくとともに、本人に「最後をどうしたいのか?」と意思を確認しておくことが、本人や家族の想いに沿った看取りケアにつながることを強調しました。