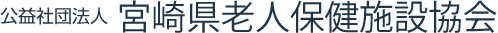10月3日(土)にシーガイアコンベンションセンターで事務長会および看護・介護研究部会主催による(「masa氏 第2弾講演会」)で、講演をしていただく社会福祉法人登別千寿会理事で、特別養護老人ホーム緑風園の「Masaさん」こと菊地雅洋総合施設長が、なんと!この日の講演会のために動画「宮崎の明日を創る介護」を作成して下さいました。
「誰かの赤い花になるために宮崎からできること」、そして「明日へつなぐ介護 心をつなげて 100年後にも色あせない介護を創ろう」と呼びかけるMasaさんの言葉が、宮崎県内各地の美しい風景やイベントの様子にのって流れていきます。5分余りの動画の中にMasaさんの介護に対する考え方がぎゅーっと濃縮されているばかりでなく、宮崎県民以上に宮崎の良さをわかっておられるのではないか、と思えるような素晴らしい宮崎の映像が盛り込まれていて、深い感動が味わえます。
この動画は講演会当日でも上映されますが、菊地総合施設長の了承を得て、当協会のフェイスブック(https://www.facebook.com/miyazakiroken)でもシェアさせていただきました。講演会を受講予定の方はもちろん、各施設で留守を預かるスタッフの方も必見の動画です。ぜひぜひご覧下さい!!